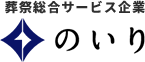一宮市、北名古屋市、江南市のご自宅で亡くなった後の流れと必要な手続き
身内が自宅で亡くなった場合、動揺して何をすべきかわからなくなるのは当然のことです。
しかし、そのような状況でも、家族が落ち着いて行わなければならない連絡や手続きが存在します。
まずは状況に応じて適切な場所に連絡し、その後の流れを把握することが重要です。
この記事では、ご家族が自宅で亡くなった直後に行うべきことから、葬儀を執り行うまでの具体的な手順について、順を追って解説します。
【まず最初に】家族が自宅で亡くなったら誰に連絡するべきか
家族が自宅で亡くなったら、まず誰に連絡すべきかを知っておくことが非常に重要です。
連絡先は、故人が生前にかかりつけ医の診察を受けていたかどうかによって大きく異なります。
この最初の対応を間違えると、その後の手続きが滞る可能性があるため、冷静に状況を判断しなくてはなりません。
亡くなったらすぐに救急車を呼ぶべきだと考えがちですが、必ずしもそれが適切な対応とは限らない点も理解しておく必要があります。
状況1:かかりつけ医がいる場合の連絡先
故人に持病があり、かかりつけ医がいた場合は、まずその医療機関に連絡します。
かかりつけ医は故人の生前の健康状態を把握しているため、持病による自然死であると判断できれば、自宅へ往診して死亡確認を行います。
その後、法的な死亡を証明する「死亡診断書」が発行されます。
深夜や休診日で連絡がつかない場合でも、留守番電話の案内や提携している病院の指示に従って行動してください。
亡くなったらすぐに遺体を動かしたりせず、医師の到着を待つことが肝心です。
この死亡診断書は、後の死亡届の提出や火葬許可の申請に不可欠な書類となります。
状況2:かかりつけ医がいない場合の連絡先
故人にかかりつけ医がいない場合や、突然死などで死因が不明な場合は、救急車(119番)ではなく警察(110番)に連絡する必要があります。
警察は事件性の有無を判断するために現場に臨場し、状況を確認します。
救急車はあくまで救命活動を目的とする機関であり、死亡の確認や診断は行えません。
警察への連絡後、監察医による検視が行われ、事件性がないと判断されれば「死体検案書」が発行されます。
亡くなったら、この死体検案書が死亡診断書の代わりとなり、その後の公的な手続きを進めるために必要不可欠な書類です。
慌てて行動しないで!自宅で亡くなった場合の注意点
家族が自宅で亡くなるという非日常的な事態に直面すると、冷静な判断が難しくなるかもしれません。
しかし、動揺から取った行動が、後の手続きに影響を及ぼす可能性があります。
特に、警察による検視が必要になるケースでは、発見時の状況を保つことが極めて重要です。
ここでは、ご家族が自宅で亡くなった場合に、慌てて行動しないために知っておくべき注意点を解説します。
むやみに救急車を呼ばない
自宅で亡くなる場面に遭遇した際、明らかに亡くなっていると判断できる場合は、むやみに救急車を呼ぶべきではありません。
救急隊は救命を目的として活動しており、死亡を確認したり、死亡診断書を作成したりする権限を持っていません。
もし救急車を呼んで搬送されたとしても、病院で死亡が確認されると、ご遺体を自宅や安置場所まで搬送し直す必要が生じます。
ただし、蘇生の可能性がある場合や、生死の判断に迷う場合は、ためらわずに119番に通報してください。
状況を冷静に見極めることが大切です。
ご遺体に触れたり動かしたりしない
自宅で亡くなる状況、特に突然死やかかりつけ医がいない場合には、ご遺体に触れたり、安易に動かしたりすることは避けるべきです。
これは、警察による検死が必要になる可能性があり、その際に死因の特定や事件性の有無を判断するための重要な手がかりを失ってしまうのを防ぐためです。
発見時の状態をそのまま保存しておくことが求められます。
故人を楽な姿勢にしてあげたいという気持ちは自然なものですが、まずは医師や警察が到着するまで、現状を維持するように心掛けてください。
発見時の状態を維持し部屋を片付けない
ご遺体だけでなく、故人が亡くなっていた部屋全体も、発見時の状態のまま維持することが重要です。
自宅で亡くなる場合、警察は事件性の有無を確認するために現場の状況を詳しく調査します。
部屋が散らかっていると片付けたくなるかもしれませんが、室内の様子や物の配置なども死因を究明するための重要な情報源となり得ます。
良かれと思って行った片付けが、かえって死因の特定を困難にさせてしまう恐れもあるため、警察官が到着して許可を出すまでは、何も動かさずに現状を保つようにしてください。
死亡確認から葬儀までの具体的な手順
医師による死亡確認、あるいは警察による検視が終わった後、ご遺族は葬儀に向けてさまざまな手続きを進めていくことになります。
これらの手続きには、役所への届け出や許可証の取得などが含まれ、それぞれに期限が設けられているものもあります。
全体的な流れを事前に把握しておくことで、混乱することなく、一つひとつの手順を落ち着いて進めることが可能になります。
ここでは、死亡確認から葬儀までの具体的な手順を解説します。
手順1:医師による死亡確認と「死亡診断書」の受け取り
かかりつけ医がいる場合は、医師が死亡の確認を行います。
医師は故人の脈拍や呼吸、瞳孔の反応などを確認し、法的に死亡を確定させます。
死亡が確認されると、医師によって「死亡診断書」が作成されます。
この書類は、故人の氏名や生年月日、死亡した日時・場所、そして死因などが記載された公的な証明書です。
死亡診断書は、この後の役所への死亡届の提出や、保険金請求など、さまざまな手続きで必要となる非常に重要な書類であるため、受け取ったら大切に保管してください。
手順2:警察による検死と「死体検案書」の受け取り
かかりつけ医がいない場合や突然死、事故死の疑いがある場合は、警察による検死が行われます。
検死とは、警察官が医師と共にご遺体の状況を調べ、事件性の有無を判断する手続きです。
検死の結果、事件性がないと判断されると、医師(監察医など)によって「死体検案書」が発行されます。
この死体検案書は、内容や法的な効力において死亡診断書とほぼ同じものであり、死亡の事実を証明する公的な書類として扱われます。
その後の死亡届の提出など、一連の手続きに必要となります。
手順3:葬儀社への連絡と遺体の搬送
医師から「死亡診断書」または「死体検案書」を受け取ったら、葬儀社へ連絡します。
葬儀社は、今後の葬儀全般の相談に乗ってくれるだけでなく、まずはご遺体を安置場所へ搬送する役割を担います。
法律上、死後24時間は火葬できないため、ご遺体を自宅か斎場の安置室などに安置しなくてはなりません。
事前に葬儀社を決めていればスムーズですが、決まっていない場合は、複数の業者を比較検討する時間的余裕がないことがほとんどです。
そのため、警察、病院から紹介された葬儀社や、インターネットで探した業者に連絡して搬送を依頼することになります。
手順4:役所への「死亡届」の提出
故人の死亡を法的に確定させるため、市区町村役場に「死亡届」を提出します。
この届出用紙は、通常、医師から受け取る死亡診断書または死体検案書の左半分が様式になっています。
届出人(親族や同居者など)が必要事項を記入し、署名し提出します。
提出先は、故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地のいずれかの役所です。
提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。
手続きが複雑に感じるかもしれませんが、多くの場合、葬儀社が提出を代行してくれます。
※のいりでは死亡届けの代行手続きを行っています。
信頼できる葬儀社を選ぶためのポイント
ご家族を亡くされた直後の混乱した状況の中で、短時間のうちに葬儀社を決めなければならないケースは少なくありません。
しかし、葬儀は故人との最後のお別れをする大切な儀式であり、費用も決して安くはありません。
だからこそ、信頼できる葬儀社を慎重に選ぶことが重要です。
ここでは、後悔しない葬儀社選びのために、確認しておくべきポイントを具体的に紹介します。
深夜や早朝でも迅速に対応してくれるか確認する
人の死は昼夜を問いません。
そのため、24時間365日いつでも対応してくれる葬儀社を選ぶことが大前提となります。
深夜や早朝に連絡した際の電話対応の丁寧さや、問い合わせてからご遺体を迎えに来てくれるまでのスピードは、その葬儀社の信頼性を測る一つの指標です。
特に、ご遺体の搬送と安置は最初に行うべき重要なことなので、迅速かつ丁寧に対応してくれる体制が整っているかどうかは、必ず確認すべきポイントです。
迅速な対応は、遺族の不安を和らげることにもつながります。
費用の内訳を明確に説明してくれるか見極める
葬儀費用は項目が多く、分かりにくいと感じる方も多いです。
信頼できる葬儀社は、費用の内訳を詳細に記載した見積書を提示し、それぞれの項目について丁寧に説明してくれます。
「葬儀一式」といった曖昧な表現で済ませるのではなく、何にどれくらいの費用がかかるのかを明確にすることが重要です。
また、見積もりに含まれていない項目や、後から追加料金が発生する可能性についても事前に説明があるかを確認してください。
複数の葬儀社から見積もりを取り、内容を比較検討することも有効な手段です。
※のいりでは事前相談も賜っております。
今後の手続きについて丁寧に案内してくれるか確かめる
葬儀社の役割は、単に儀式を執り行うだけではありません。
ご遺族の負担を軽減するため、役所への死亡届の提出や火葬許可証の申請といった煩雑な手続きを代行してくれるなど、多岐にわたるサポートを提供します。
優れた葬儀社は、葬儀そのものだけでなく、葬儀後の法要や香典返し、さらには相続に関する相談など、今後の流れについても丁寧に案内してくれます。
遺族の心に寄り添い、さまざまな疑問や不安に対して的確なアドバイスをくれる担当者がいるかどうかは、葬儀社を選ぶ上で非常に大切な判断基準となります。
まとめ
自宅で亡くなったという事態に直面した際は、まず故人にかかりつけ医がいたかどうかで最初の連絡先が変わります。
かかりつけ医がいる場合はその医療機関へ、いない場合や死因が不明な場合は警察へ連絡することが基本です。
その後は、医師による「死亡診断書」または警察の検視を経て発行される「死体検案書」を受け取り、葬儀社を手配します。
役所への死亡届の提出や火葬許可証の申請といった手続きを経て、葬儀の準備へと進んでいきます。
突然のことで動揺する状況ですが、一連の流れを把握しておくことで、落ち着いて故人を見送るための行動をとることができます。